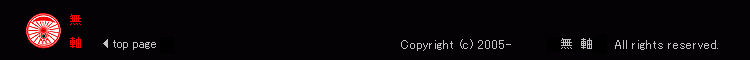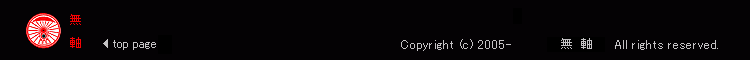これまで市販品の8番分岐器を二台組み合わせてました。
しかし、外見、特性共に芳しくなかった為、
周辺工事を行ったついでに、自作品に置き換えるべく、設置準備工事を行いました。
工作の都合上、片渡り線ベースは別ブロックとし、既に枕木敷設を始めています。

製作法詳細は左目次から8番分岐器も参照下さい。
並枕木は幅が 4.5mm なので、
サーキュラソーを使って、5×3mmの桧棒から幅を 0.5mm 詰めて作ります。

三本まとめて切断しています。
なお、メタルソーで木を切ると、どういうわけか切れ味が非常に劣化するので、
木工用と金工用の刃は、区別した方が良いかもしれません。
が、当局局長は、きわめて面倒くさがり・横着なので、そうしていません。

そこのカントは、曲線外側にt1の桧材を貼って表現します。
緩和曲線部は、サンダー等で薄く削って、滑らかにカントが変化するようにします。

分岐枕木の方は幅が5mmなので、5×3mm桧棒を所定の長さにカットして貼り付けます。
並枕木と分岐枕木の違い、枕木間隔の変化が、楽譜のようでもあり見ていて楽しい・・・
ベースボードは、t13 の桐集成材です。狂いが生じにくい上、
軽く柔らかく、固い年輪もないのでスパイク時に苦労しません。

水で少し薄めて、塗りムラが残る様、筆塗りしました。

フライス盤では、手ヤスリでは到底不可能な形状の切削ができますし、
加工時間、精度とも比較になりません。
今回の、片渡り分岐器用レール一式(ストックレール・ノーズレール・トングレール)削るのに、
一日半ぐらいで済みました。

材料の粘りが強いので、表面の加工痕は少々荒れ気味です。
実物に習って、トングレール趾端(矢印)も丸く削っています。
趾端が尖ったままだと、ここにフランジが引っ掛かり、レールに乗り上げ脱線・・・
の確率が高くなります。
#135引抜レール(OJフレキに使用のもの)も、入手困難な時期が続きましたが、
幸い、IMONさんで入手可能になりました。
今回、渋谷店まで出掛ける元気が無く、通販で購入しました。

桐集成材に仮にスパイクして、位置・角度を出しています。
ハンダ付けを苦手とする当局が云うのもなんですが、
ここ最近、ハンダフラックスは、Sフラックス(アサダ)(塩化亜鉛+塩化アンモニウム系)を使っています。
塩化亜鉛水溶液より、ハンダ流れが良いような気がします。
共晶ハンダだと薄くスーッと広がるので、キサゲの必要がほとんどありません。
これは、ライブスチーマーの方から教えて頂きました。

もたもた作業していたら、焦げてきました。

トングレール趾端下は洋白板を嵌め込み、スライドする様、後でグリスを塗布します。
レール高さを合わせる為、フログ床板の下も同様に削ります。

レールは、スパイク前に塗装しておきます。
写真下の直線側ストックレールからスパイクしていくと、位置決めが容易です。
レールヘッドが線路中心線から12mmの位置にスパイクします。
次に、床板の付いたフログ部、
その次にリードレールと進みます。
リードレールの曲率は、図面の座標を参照します。

市販分岐器と比べて、トングレールがかなり短いのが判ります。
ベースボードに開いた四角い穴には、分岐器転換用のサーボモーターが入ります。

スラックは、実物と同じ位置に、ほぼ同量、設定しています。
あまり知られていない事ですが、トングレール趾端で、
既にスラック量 0.5mm(実物は18mm)設けてある事に注意です。
驚くべきことに、旧篠原製のOJ分岐器も、大体そのようになっていました。
8番分岐の場合、スラックを設けないと、
D50のようなホイールベースの長い機関車の通過が、
計算上でもかなり苦しくなります。

ガードレールは、チェックゲージに十分注意して設置し、
二軸貨車など繰り返し通して、割り込み等が発生しないか確認します。
チェックゲージは当局では、22.5mm に設定しています。
なお、旧篠原8番分岐器のチェックゲージは、旧規格車輪の通過を考慮したためか、
22mmとなっており、稀に割り込みが発生する事があります。
ガードレールを移設することが根本的解決となりますが、
当局では、ノーズレール鼻端を丸く削ることで、応急的に対処しています。
(丸く削る事で、鼻端にフランジが引っ掛かり、
ノーズレールに乗り上げ、脱線というような事態が辛うじて防げる。)

こうしてみると、OJゲージの線路の美しさは別格に思えてきます。